私たちの食卓は、日々の暮らしを支えると同時に、気候変動や環境保全、地域社会の活性化など多様な側面に深く関わっています。2021年に京都で誕生した非営利団体「一般社団法人FEAST」は、こうした複雑な食と農の課題を、市民参加型のアプローチで乗り越えていくことを目指してきました。総合地球環境学研究所(RIHN)の2016年度から2020年度までの5年間のプロジェクトから出発したFEASTの各メンバーは、2021年から2024年にかけてどのような活動を展開してきたのでしょうか。本記事では、大きな4年間の活動を振り返ります。
2021年:基盤づくり
2021年3月末、RIHNの研究プロジェクト終了に合わせて正式に設立されたFEASTは、立ち上げから積極的にイベントを開催。京都信用金庫「Question」のイベントウィークやアースデイ in 京都で、地域の皆さんと対話する場を数多く設けました。また、地球研時代からの成果やネットワークを反映した書籍『みんなでつくる「いただきます」』の出版などを通じて、持続可能なフードシステムへの転換を社会に向けて発信しました。
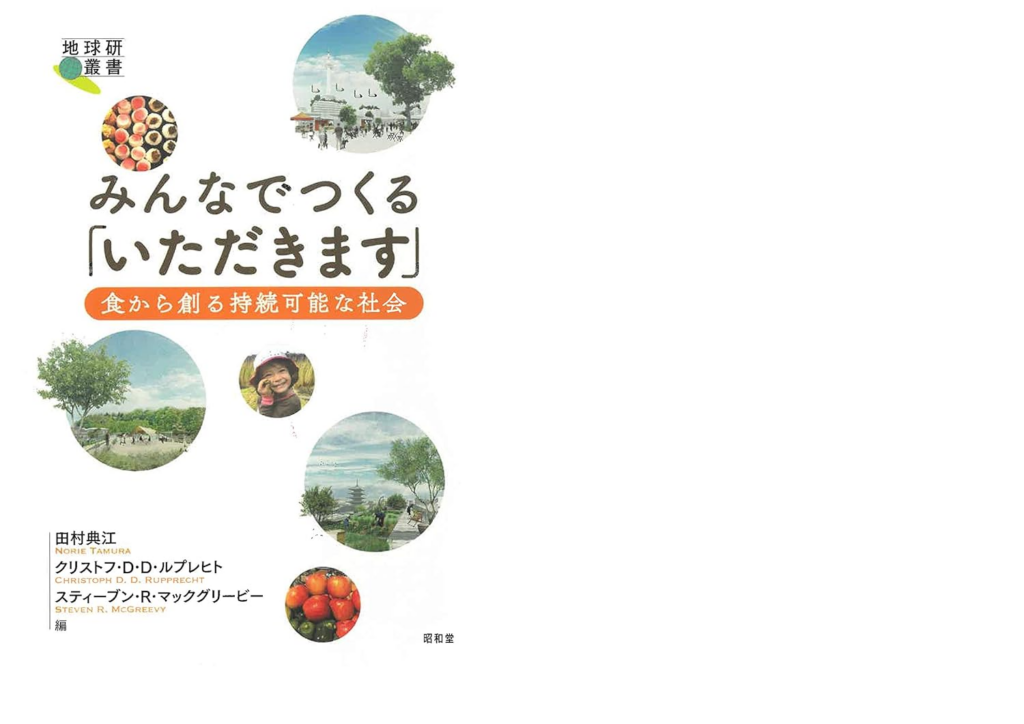
また、コロナ禍での第3回シリアスボードゲームジャム(SBGJ)のオンライン開催もあげられます。2日間で社会課題をテーマにボードゲームを創るというイベントには40名あまりが参加し、食の未来を楽しく学ぶ新しいゲームがいくつも誕生しました。
2022年:「ハブ」としての役割
2年目に入り、FEASTはイオン1%クラブが主催する高校生・大学生向けの国際交流プログラム「アジアユースリーダーズ」への協力を通じて、若い世代に食や農を通じた持続可能な社会づくりのための国際的な報告の場を作りました。FEASTメンバー自身も欧州やアジア諸国へ研究拠点を広げ、オンラインで知見交換する取り組みも活発化し、日本各地・国外のコミュニティをつなぐハブとしての役割が明確になってきました。
一方、地域では亀岡オーガニックアクション(亀岡OA)が育てた有機米が小学校の給食に本格導入されるなど、自治体との協働が具体的な成果を生み始めました。また、京都府内の有機農家と八百屋が連携する京都オーガニックアクション(KOA)が稼働するなど、都市と農村を結ぶ仕組みづくりが広がりました。※参考:田村典江. (2022). 公開地域シンポジウム報告/地域から食と農を組み直す-亀岡オーガニックアクションの取り組み. フードシステム研究, 29(3), 139-145.
そして、第4回SBGJは熊本市で実施。初めて地域の図書館と共催し、「食卓からは見えない景色」をテーマに、参加者が斬新なアナログゲームを2日間で開発するイベントとなりました。
2023年:ポストコロナの世界
気候変動への関心が世界的に高まる中、FEASTも多彩な対話イベントを支援。春の「オーガニック給食フォーラム」では自治体の担当者や農家、研究者がオンラインで意見を交わし、実践事例や課題を共有しました。新型コロナの感染拡大がおさまり、長野県小布施町では在来種野菜の料理会など、草の根の実践が再び活気を取り戻しました。
また、名古屋で開催された第5回アジア太平洋圏食農倫理会議では、台湾やタイ、インドネシア、ミクロネシアなどの国からの実践報告と倫理的考察が寄せられました。

2024年:論文集の刊行に向けて
4年目に突入したFEASTは、食や農の問題を「単なる消費」から「未来を創る行為」へと位置づけ、社会全体が新たなストーリーを共有できるよう論文集の刊行に取り組んでいます。また、これまで培ったフードポリシー・カウンシル運営のノウハウを広く共有し、各地域で住民が主体的に食と農の未来を描けるようなツールの作成(「未来の給食」など)を計画中です。林業や漁業を含む多角的な地域循環を議論する取り組みも拡充し、今後も新しい学びと想像力を育む場を作ることを目指しています。